奇蹄目 サイ科 シロサイ属 ミナミシロサイ Ceratotherium simum simum
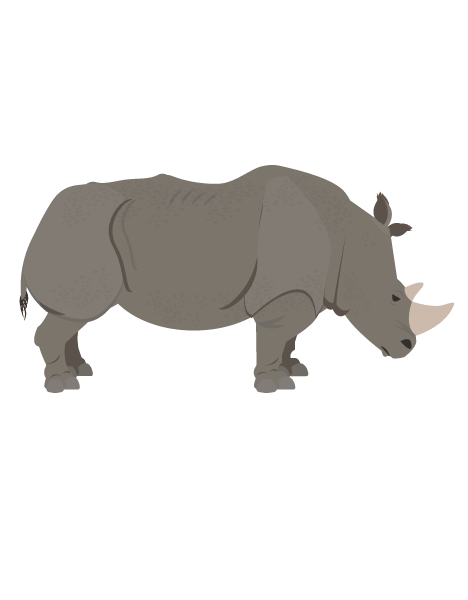
シロサイ(ミナミシロサイ)のイラスト
サイの中でも最大級の種で、体重は最大2~3トンに達する。
これは身近なもので例えるなら小ぶりな自動車2,3台分であり、アフリカゾウに次ぐ陸上最大級の哺乳類である。
全身にほぼ毛はなく、特に成獣では耳先と尻尾の先にしか目立って生えていない。
動物園で「シロサイ」という名前で飼育されているのはほぼ確実にこの「ミナミシロサイ」である。
というのも、同じく亜種である「キタシロサイ」は飼育下にある高齢のメス2頭を残して2008年には野生絶滅、2018年に最後のオス個体が死亡しており、事実上「絶滅」しているからである。
凍結保存された生殖細胞を用いて、ミナミシロサイを代理母として復活させる計画もあるようだが、過酷な道であることは想像に難くない。
また、シロサイというとよく言われるのが「体色が白いからシロサイなのか」という疑問である。
これの答えは、「NO」である。
シロサイの名前の由来として有力とされているのは、「最初のころは幅の広い口を持つことからWide rhinoceros (ワイド ライノサラス)と呼ばれていたものが、書き間違いor言い間違いor聞き間違いによってWhite rhinoceros (ホワイト ライノサラス)と呼ばれるようになって定着してしまった」というものである。他の説(アフリカーンス語のwijde由来等)もあるが経緯は大体同じである。
日本に名前が伝わるころには既に白のほうになっていたようで、日本でも直訳して「シロサイ」と呼ばれるようになったようだ。
ちなみにシロサイより後に名前を付けられた「クロサイ」は、こちらも体色が由来ではなく「シロ」じゃないほうということで対の「クロ」があてがわれたのだとか。
さて、本来の名前の由来であった幅広の口であるが、これは彼らの食性に適した形状となっている。
シロサイたちは地表の草をむしり取るように食べるのだが、その際一度の咀嚼でより多くの草を抜き取るには接地面が広いほうが効率が良かったのである。
イメージしづらい方は、その辺の雑草が生えている道端で、親指と人差し指の2本指でつまんで抜くのと5本指全部使ってむしるのと、どっちのほうが1回で草が多く取れるか試してみるといい。
また、シロサイの口先をよく見てみると、門歯(切歯、前歯)が無いことが生体でも骨格標本でもよく分かるが、これは「角を突き合わせて激しくぶつかり合う喧嘩をするサイたちにとって、衝撃で怪我しやすい門歯は邪魔だったからでは」という説が濃厚である。
クロサイも同様に門歯はないが、他のサイ(インドサイやジャワサイ)では少ないながら門歯があるものもいる。
さらに、骨格標本になると見当たらないのは門歯だけでなく、彼らの象徴である角もない場合が大半である。(ついてたら多分後から付け直している。)
これはサイたちの角が私たちの髪や爪と同様ケラチンというたんぱく質でできており、骨ではないからである。(つまり皮膚に張り付いている…というより分厚い皮膚上の塊である。)
よくサイの角は漢方薬として重宝されるといわれるが、その薬効はおそらくプラセボ効果(思い込み)によるものであり、私たち自身の髪や爪を煎じて飲むのと成分的には大差ないのである。
それでもサイたちの角への期待を持つ人や、トロフィー(装飾品)として求める人がいるので、サイの角は違法かつ高価で取引されてしまう。
さらには2019年から蔓延した某流行病の影響もあり、現地で需要がなくなり生きて行けなくなった観光業関連の人が、生きていくためにサイの密猟に手を出してしまうなど、ここ数年で新たな問題も発生していたりする。

コメント