奇蹄目 サイ科 クロサイ属 クロサイ Diceros bicornis
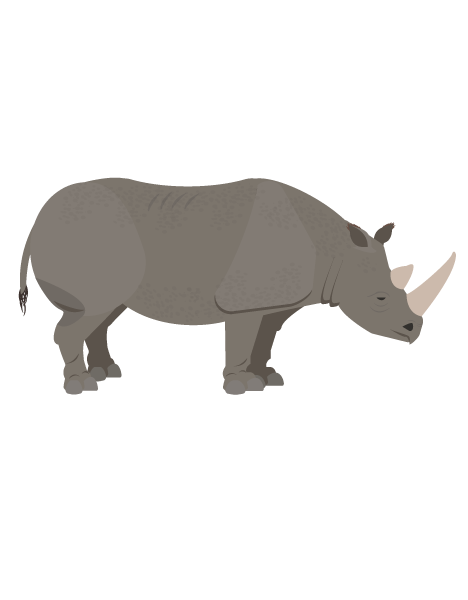
クロサイのイラスト。
サバンナなどの低木がある地域に生息するサイの仲間で、角は2本、体重は最大でも1.3トンほどで、シロサイと比べると小柄である。
生息地はシロサイと同じくアフリカ大陸であり、どちらも密猟などが主な原因となって絶滅の危機に瀕している。
地面の草を主食とするシロサイと違い低木の樹葉を主食としており、枝についた葉を巻き込み臼歯で嚙みちぎる。
より多くの葉を掴みやすくするため、シロサイと異なりよく動く尖った口先になったとされ、口先に注目すれば体格はともかく外観が似通っているシロサイとクロサイを見分けやすくなる。
シロサイの頁でも書いているが、シロサイとクロサイは色で区別されているわけではない。
では、シロサイは白く、クロサイは黒くなることは無いのか…というと、実は名実ともに白or黒になることもある。なんなら赤茶色になることもあるし、その色の変化はどのサイでも起こりうる。
どういうことかというと、彼らサイの仲間は、日光や虫や乾燥から肌を守るために泥浴びをよくするのだが、それを繰り返すことによって「長く生息しているその地域の土の色」に染まっていくのである。
もちろん刺青のようにがっつり染色されるわけではないので、環境が変われば徐々に色も変化する。
特に動物園間で移動があった場合はそれが分かりやすい。
また、サイの仲間は総じて皮膚が分厚いことで知られており、太めの注射針さえ簡単に弾き使い物にならなくなってしまう。
治療や採血などの際は、比較的皮膚の薄い耳の背面が使われることが多い。
ちなみにそんなサイの耳(聴力)はかなり優れており、嗅覚と合わせることで、あまり優れていない視力の代わりに周囲の状況把握に大活躍している。
ラッパのような形で集音性抜群なだけでなく、前後によく動くので、耳を見ればそのサイが「どこの何を気にしているのか」が分かったりする。
ただ、結局視力は悪い(おそらく数メートルも離れれば形を認識できない)ので、何かに驚いたり、興奮したり、パニックになった場合は「相手が何なのかも確かめずに全力(時速約50km)で音のした方に突っ込んでくる」ので非常に危険である。

コメント